「おこづかいは、いつぐらいから渡せばがいいの?いくら?」
「手伝いしたらあげるべき?それとも毎月きまった金額?」
「SNS課金は、どこまでOKにしたらいいの?」
親はここで迷う=むしろ正解。ちゃんと考えてる証拠です。
この記事では
- いつからおこづかいを始める?
- 平均いくらくらい?
- 定額制と成果報酬制って何が違う?
- ゲーム課金はどう線引きする?
を“親子でそのまま話せる会話”と“すぐ使えるルールシート”にしてまとめてみました。
ルールシートは、今日からおうちで使える実用版です。
💰 おこづかいは「何才から渡すべき?」の正解
「これ買いたい」「お金が必要」という自覚が子どもに出てきたらスタートでOK。だいたい小学校低学年くらいから始める家庭が多い。
理由は2つ。
- お金を「欲しい物と交換するチケット」だと理解しはじめるのが小学校年代だから。
- 自分で選んで、自分で反省する体験(計画→購入→なくなる→次回に活かす)ができる年齢だから。
学校では、そこまで丁寧に教えてくれません。家庭がいちばんの実践の場になるのです。
親のひと言:
「これからは、自分のお金を自分で考えて使う練習をしていこう」
ここで“信頼されてる感”を持たせると、こどもはかなり乗ってきます。
👦 みんなどれくらいもらってる?「おこづかい平均額」

これは、読者が知りたいところなのでいくつかデータを👇
● 小学生
- 低学年(小1〜2):平均おこづかいはだいたい月900〜1,000円台 中央値800円
- 中学年(小3〜4):平均値1,100円前後 中央値1,000円
- 高学年(小5〜6):平均値1,600円くらい 中央値1,000円
→ 小学生の渡し方は「毎月決まった額(定額制)」が約4割でいちばん多い、次いで「必要なときだけ渡す」が約3〜4割。ICT教育ニュース
中央値とは・・・一部の高額なおこづかいの影響を除外して、より一般的なおこづかい水準を把握するために使われる。
● 中学生
- 月3,000円台というデータが多い(平均3,390円という調査もある)。TABI LABO
- 部活・友だちとの外食・推し活など“交際費”が一気に増えるので、金額より「使い道の優先順位づけ」の会話が大切。
● 高校生
- おこづかいは、平均で月3,927円(2024年11月の学研教育総合研究所の調査)。学研
- 別の高校生アンケートでは、平均月5,279円という報告もあり「毎月定額で渡している」が約6割と主流。進路ネット
- さらにアルバイトで稼ぐ子は、平均月7,239円程度の収入というデータも出ている。学研
👉 まとめると
・小学生:1,000〜1,500円くらいが多い
・中学生:3,000円台くらい
・高校生:4,000〜5,000円台(+バイトで増える子も)
というのが2024〜2025年の実勢おこづかいです。
ここが大事な注意点:
「金額」よりも「ルール」と「振り返りの時間」のほうが子の金銭感覚には効きます。
✅おこづかいの渡し方3タイプ(どれ選べばいい?)
おこづかいの渡し方を3つのタイプにまとめました。
① 定額制(ベーシックインカム型)
毎月◯日に◯円あげる。基本的に条件なし。
【親のメリット】
・管理がシンプル
・子どもが「今月あといくら残ってるか」を計算する習慣がつく(予算感覚)
【デメリット】
・“やれば増える”が学びにくい
・「なんでこんなに早く使ったの?」の親子の衝突が起きやすい
向いてるのは:
→ 小学生中〜高学年くらい。まだ「稼ぐ=働く」の前にまず「予算管理」を覚えたい時期。
親の声がけ:
「今月は、おこづかいの中でやりくりしてみよう。使い切ったら来月まで待つ練習もやってみよう。」
② 成果報酬制(お手伝い・行動と引き換え)
「お皿洗い1回50円」のようにやったことに対して支払う方式。
【親のメリット】
・“働く=価値を生む=対価をもらう”が伝わる
・子どもの「手伝うモチベーション」が上がる
【デメリット】
・逆に「これやらないとゼロ円」で家の基本的な手伝いまで“全部お金化”されがち
・親も管理がめんどう(毎回いくらって記録が必要)
向いてるのは:
→ 家事分担を教えたい家庭/「お金は、ありがとうの結果だよ」(第1話のテーマ⬇️)を実感させたいとき。
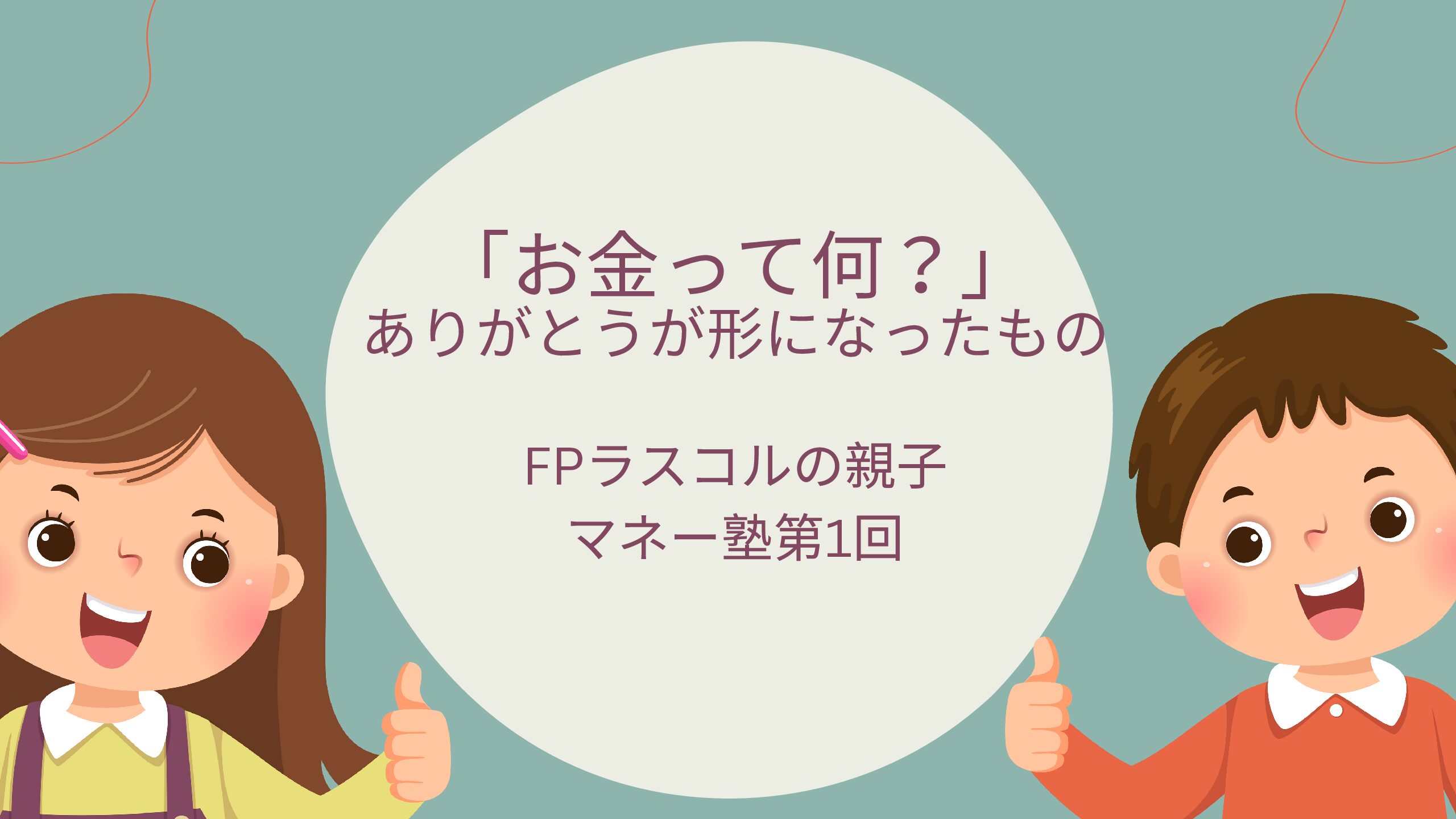
親の声がけテンプレ:
「手伝ってくれて助かったよ。これは“ありがとう”のお金ね」
⚠️注意
なんでもかんでも「やればお金になる」とすると、家庭内の「思いやり」まで商取引になるリスクもあるので、あくまで“追加タスク”にするのがコツ。
→ 例:普段の自分の片づけ=無償の行動/家の大掃除を手伝った=報酬OKのような線引き。
③ ハイブリッド型(いちばんオススメしやすい)
“基本の定額+手伝いボーナス”の合わせ技。
例:
・月1,000円は固定で渡す(予算管理の練習)
・家のサポートをしたらプラスαで追加(労働=お金の実感)
これは最近よく推奨されてるやり方で、「定額」+「都度プラス」でもらう家庭は多いという調査もあります。
FPラスコル的にもこれがいちばんバランス良いと思います。
なぜなら子どもが
- “予算を管理する力”
- “自分で稼ぐ感覚”
を同時に身につけられるからです。
🙅「これはダメ」はやめてOK。「枠を決める」に変える
親子ケンカになること:ゲーム課金、推しグッズ、ガチャ。
親が「そんなことダメ!」と強制すると、子どもは“こっそり、内緒で、親に言わず”の方向に走りやすい。
それは一番あぶないパターンです。国民生活センターにも未成年の無断課金やSNSきっかけのトラブル相談が繰り返し寄せられています。
ですので、いきなり禁止するよりも「ルールにする」のが安全。
おすすめはこの3つ:
① 上限ルール
「月額の中でゲーム課金は500円までOK」
→ 500円以内なら自分の判断で自由に使っていいという安心を与える
→ 子どもは、隠さず言いやすい
② 相談ルール
「こっそり課金しない。買う前にスクショして“これ買っていい?”って聞く」
→ 内緒でOKと決めたものは詐欺の入口になりやすいので、親と行動を共有する。
③ 反省ルールではなく“振り返りタイム”
月末に「今月いちばん良いお金の使い方は?」を表彰する。
これは第5話の「お金は幸せの道具」とつながる⬇️。

「誰かを喜ばせたお金」や「思い出に残る体験のお金」をほめる時間を作ると、自然に使い道も良くなっていくという示唆が行動経済学の研究からも得られています。
🧑🧑🧒家族で合意すべき「おこづかい5原則」(ルールシート印刷して貼れます)
- 毎月〇日に〇円わたします(基本給=定額制の部分)
- 手伝いをしたらボーナスが出ます(成果報酬の部分)
- 使い道は自分で決めてOK。ただし、上限ルールは守る
- こっそり課金・こっそり借金はしない(必ず相談する)
- 月末に「今月いちばんナイスなお金の使い方」を家族みんなで発表する
「今月のMVP支出」を褒める時間があると、子どもは“お金=しあわせをつくるもの”として考えはじめる。
これは、幸福度の高いお金の使い方(体験・人のため・自分の成長)にお金を振り向けると満足度が上がるという複数研究と合っています。
✨まとめ(親へのエンディングメッセージ)
- 正解の金額よりも話し合えるルールが大事。
- 定額制だけじゃなく、ハイブリッド型にすると「管理する力」と「稼ぐ力」が両方育つ。
- 「ダメ」というのは、こっそり行動を生むもとに。
これからの時代に必要なのは“一緒に中身を決める”おこづかい教育。 - おこづかいは小さな家計。つまり“人生の予行演習”なのです。
親子で楽しんで決めたルールは、教育ではない。家族の作戦。
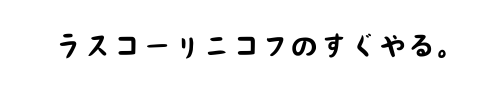



コメント