サラリーマンを辞めて自営業になると「厚生年金部分がなくなる」という現実にあたります。
厚生年金の時は会社が半分負担してくれます。一方で、自営業になると国民年金(基礎年金)のみになります。
「老後の年金大丈夫かな…?」と会社員を辞めてフリーランスになった人は思うかもしれません。そう心配するのも無理はありません。
しかし、私(ラスコル)は将来いくらもらえるかを心配するよりは、起業で稼いで投資等で運用して将来に回せばいいという考えです。
将来を心配される人には、国民年金基金という選択肢があるということで今回検討をしてみます。
私は加入を予定してません。ですので“冷静な目線”でメリット・デメリット・他制度との違い・節税効果を整理します。
この記事では、これから開業する人が「まず何から考えればいいか」を一緒に学べるようにまとめました。
👉 まずは、今のご自身の月キャッシュを確認しましょう。
「売上が低い月でも安心して払える金額」があなたのスタートライン。
それが決まったなら、国民年金基金・iDeCo・小規模企業共済のどれを利用するか検討しましょう。
💰国民年金基金とは?
会社員の「厚生年金」にあたる“上乗せ部分”を自営業者が自分で用意できるようにした公的な年金制度。
いわゆる「国民年金(基礎年金)の2階建て」の2階部分。
- 老後の受取額があらかじめ決まっている(確定給付型)
- 掛金は全額所得控除(節税になる)
- 一生もらえる終身年金タイプも選べる
- 途中で原則やめられない(=固定費になる)
👉国民年金基金は「将来の年金(毎月の生活費)をいまのうちに自腹で太らせる制度」です。

📈制度比較表:どれが自分向き?
| 制度名 | タイプ | 目的 | 節税効果 | 受取時期・方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民年金基金 | 確定給付型(公的) | 老後の年金上乗せ | 掛金は全額所得控除(社会保険料控除) | 原則65歳~(終身または一定期間) | 終身年金あり=長生きリスクに強い / 遺族一時金タイプあり | 原則途中解約しにくい / インフレに弱い可能性 / 付加年金と同時不可 |
| iDeCo | 確定拠出型(自己運用) | 老後資産づくり | 掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除) | 60歳~75歳(年金or一時金) | 運用益が非課税 / 自分で配分できる | 元本割れリスク / 60歳まで引き出せない |
| 小規模企業共済 | 積立退職金型 | 廃業・引退資金 | 掛金は全額所得控除 | 廃業・退職時 | “自分の退職金”をつくれる / 節税が強い | 短期解約だと元本割れリスク |
| 付加年金 | 上乗せ型 | 国民年金の底上げ | 一部所得控除 | 65歳~ | 月400円という超低コストで将来の年金額アップ | 国民年金基金とは同時加入できない |
👉ぜんぶ同じ“老後の積み立て”のように見えますが役割も出口も違います。

💴掛金と上限の考え方

- 国民年金基金は、「口数制」でいくら払うかをある程度選べる
- 年齢や選ぶ給付タイプによって掛金額が変わる
- 掛金は途中で増減できるので、将来の売上に合わせて調整することも可能
- 「国民年金基金+iDeCo」の合計は、第1号被保険者だと月68,000円(年816,000円)が上限目安になる
つまり「国民年金基金にどーんと入れる=iDeCoの枠がそのぶん小さくなる」ということ。
節税枠は有限。どのように振り分けるかは戦略しだいです。
⤴️節税の威力
国民年金基金の掛金は、支払った全額が「社会保険料控除」になります。
経費とは別枠で所得から引ける=課税所得を直接下げられる。
たとえば
- 月2万円×12ヶ月=年間24万円 掛けたとする
- 課税所得が24万円分下がる
- 結果、所得税+住民税で数万円レベルの節税になることもあります
“税負担が軽くなって老後の年金も増える”。フリーランスにとっては、やさしいしくみです。
私が「検討する余地があるかな」と思うのはこの節税部分かな思います。
売上が安定してきて、税金を重く感じてきたタイミングで効いてくる。
所得別・国民年金基金の節税効果早見表(2025年版)
| 課税所得(約) | 合算税率 | 掛金月1万円(年12万) | 掛金月2万円(年24万) | 掛金月3万円(年36万) | 掛金月5万円(年60万) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万 | 30.42% | 36,504円 | 73,008円 | 109,512円 | 182,520円 |
| 500万 | 30.42% | 36,504円 | 73,008円 | 109,512円 | 182,520円 |
| 700万 | 33.483% | 40,179円 | 80,358円 | 120,537円 | 200,895円 |
| 1,000万 | 43.693% | 52,431円 | 104,862円 | 157,293円 | 262,155円 |
※実際の節税額は所得控除後の税率・扶養・社会保険料などにより変動します
✅ 表の見方
たとえば、年収500万円の個人事業主が
国民年金基金に「月2万円(年24万円)」積み立てた場合、
年間で約7.3万円の節税が見込めます。
つまり、実質の掛金負担額は「24万円-7.3万円=16.7万円」。
この16.7万円が“税金を前払いして将来年金で返ってくる”感覚。
節税+老後資金づくりのどちらも取れるのが国民年金基金の魅力です。
⬇️将来の年金額のシミュレーションができます。

メリットとデメリットを冷静に見る
✅ メリット
- 将来の年金額が“ほぼ決まってる”安心感(投資みたいに上下しない)
- 終身年金タイプを選ぶと90歳でも95歳でも支給が続く=長生きが怖くなくなる
- 掛金が全額所得控除=節税しながら老後資金を用意できる
- 遺族一時金ありタイプもあるので、完全な掛け捨てにはなりにくい
- 自分の都合で掛金(口数)を増減できる
⚠️ デメリット
- 原則として途中でやめられない
→ つまり“毎月の固定費”。売上が落ちたときも払い続けなければいけない重さがある - インフレに完全に追いつけないリスク
→ もらえる額が基本的に決まっているので、物価がメチャ上がると実質価値が目減りする可能性がある - 国民年金基金に入ると、「付加年金(月400円で年金上乗せ)」は同時に使えない
→ どっちを使うか作戦を立てる必要がある - iDeCoと違って運用で増える“ワンチャン上振れ”はない
→ 逆にいえば安定なのですが「増える期待値」という意味ではiDeCoに軍配が上がる場面もあります
私の今の立ち位置から考える
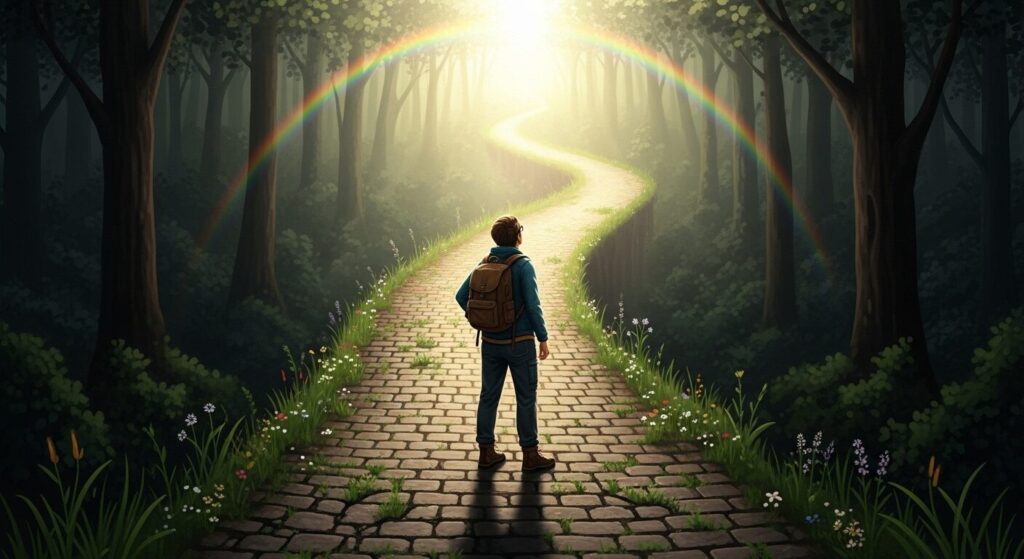
今のところ私は国民年金基金の加入を検討してません。
ただ、魅力的な理由が2つあります。
理由1:節税しながら老後資金を作れること
ただ貯めるだけでなく、課税所得を下げてくれるのはフリーランスにとっては魅力的な“防具”。
理由2:終身年金があること
「いつまで生きるかわからない老後問題」は、50代を前にすると急にリアルになります。
厚生年金の2階部分(=会社員のときの安心ゾーン)が消えた今では、その穴をどう埋めるかは避けて通れないですね。だから、フリーランスでしっかり稼いでおく😀
一方で検討される方に考えていただきたいのが👇
- 開業していきなり固定費を増やすのはリスク⚠️
- 「月いくらならやりくりできるか」を先に決めてから加入する
- いきなりMAXで掛けるのではなく、少額からスタートする→売上に合わせて口数を増やすことが現実的だと思います
❓Q&Aコーナー
Q1. 国民年金基金とiDeCoは両方やるべき?
→ やってもOK。ただし2つの合計で月6.8万円という上限がある。
あなたの性格で選ぶなら:
- 安定して決まった年金がほしい → 国民年金基金寄り
- 資産を増やすチャンスも取りたい → iDeCo寄り
両方に少しずつ振る「ミックス型」もあり。
Q2. 付加年金と国民年金基金は同時に加入できる?
→ 加入できません。
- 開業初期は「付加年金(月400円)」で将来の年金額の底上げ
- 収入が安定してきたら、付加年金→国民年金基金に切り替えて本格積み上げ
という方法も。
Q3. 掛金は経費になるの?
→ “経費”ではなく「所得控除」。
確定申告で「社会保険料控除」にすることで、課税所得自体を下げられるます。これが節税の肝です。
Q4. 途中でやめられないって聞いてビビったんだけど
→ そこが注意ポイント⚠️。
国民年金基金もiDeCoも「いざってときにすぐに現金化」はできない制度。
だからこそ月額を見栄で決めないで。
売上ゼロの月でも払える額にしておくのが現実的な路線です。
☀️まとめ:いま何を決めればいいのか
フリーランスになったら、厚生年金の2階部分がなくなります。
「老後どうする?」は、開業初期からスタートしてます。
といっても、いきなり満額を積み立てる必要はありません。
現実的な順番は👇
- まずはキャッシュフローの確認
→ 「毎月いくらまでなら老後用に用意しても生活が行き詰まらないか?」を数字で決める - 付加年金や国民年金基金などを利用して“年金を厚くするタイプ”を押さえる
- 売上が安定してきたら、節税も考えて国民年金基金やiDeCo、小規模企業共済の配分を決める
- とくに節税メリット(所得控除)は、一定以上の利益が出ると一気に効いてくる
読者のみなさんは、ぜひ「額」ではなく「長く続けられるか」で考えてください。
老後資金は、一発の勝負ではなく続けていく設計です。
✨関連リンク

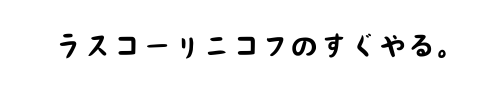



コメント