健康保険の切り替え時は、どうしたらいいか悩みますよね。
私は以前「協会けんぽの任意継続」を続けていましたが、更新をやめて転職先の健康保険に加入する流れになりました。
この記事では、その際に生じる 「空白期間」・・・一時的にどの健康保険にも入っていない状態について調べて、当時の体験を通してわかったことをシェアします。
この記事を読めば、同じように「次の保険証が届くまで不安…」という人も安心できるはずです。

👦私のケース:任意継続終了から転職先の健康保険へ
- 協会けんぽ任意継続は、 毎月10日までに保険料を払わなければ自動的に資格喪失。
- 新しい仕事は 、29日からスタートでした。
- 新しい職場が社会保険の手続きをしてくれるが、保険証が手元に届くのは数日〜1週間後。
つまり、協会かんぽの任意継続の資格が喪失してしまうと「保険証がない期間」が必ず発生します。
「では病院に行きたい場合にどうする?」と不安になって調べました。
🏥空白期間に病院へ行ったらどうなる?
- いったん10割(全額)を自己負担で支払う。
- 後日、新しい保険証が届いたら「資格取得日」にさかのぼって有効になる。
- 医療機関または保険者に申請すると差額(7割分)が戻ってくる。
「完全に保険が効かない」というわけではなくて、立て替え払いになる可能性があるということです。
ただし、これは「新しい職場で社会保険に加入することが確定している」場合に限られます。
もしもアルバイトが短期・週20時間未満などで社会保険の加入条件を満たさない場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。
🏢アルバイトをする人で賃金未確定でも保険証は発行される?

これ気になる人が多いはずです。
次の職場がアルバイトの人で「まだ時給や勤務時間が確定してないけど、保険証って出るの?」という疑問。
大丈夫です。
- 会社は「資格取得届」を提出するときには、見込みの賃金額を基に「標準報酬月額」を設定します。
- たとえば「時給1000円×週30時間=月12万円見込み」といった形です。
- 実際の給与があとから変わっても毎年の「定時決定」や「随時改定」で修正される仕組みがあります。
つまり、賃金が確定していなくても加入手続きは進みます。
✅2025年からの大きな変化:紙の保険証はなくなる
ここでさらに重要なポイント。
- 2024年12月2日以降、新規の紙の健康保険証は発行されなくなりました。
- 代わりに「マイナンバーカード(マイナ保険証)」が基本になります。
- もしマイナンバーカードを持っていない、あるいは登録していない場合は「資格確認書」が交付されます。
これからは「紙の保険証が届かない」が普通になります。今後は「マイナ保険証連携か資格確認書になります」と説明を受けました。
🫤読者が得られる「不安解消」
この体験を通して感じたのは、「知らないと不安になる」点です。
この記事を読んで、次のことがわかります。
- 賃金未確定でも雇用契約があれば保険加入はできる。
- 空白期間中に病院へ行った場合も、後日払い戻し可能。
- 2025年からは紙の保険証は原則なくなる。
- マイナンバーカードを持っていない場合は「資格確認書」で対応できる。
つまり、保険証が手元に届くまでの「不安な空白時間」を正しく理解すれば、安心して過ごせます。
☀️まとめ:不安を解消して次の一歩へ
私も最初は「無保険になったらどうしよう」と焦りました。
しかし、制度上きちんと守られていることがわかりました。
- 任意継続をやめても、新しい職場で加入条件を満たせば健康保険は切れない。
- パートやアルバイトの場合に賃金未確定でも「見込み額」で処理される。
- 紙の保険証がなくなってもマイナ保険証や資格確認書がある。
「知らない」ことが一番のリスクです。この記事が、同じように悩む人の安心材料になればうれしいです。
✨関連リンク

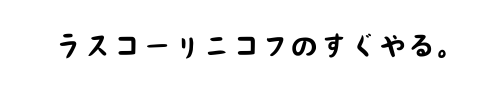



コメント