家族の相続や認知症を発症したときなど、
「保険に加入しているのは聞いていたけど、どの保険会社に加入していたのか?」
「保険契約があるのかどうかもまったくわからない」
そんな不安を解消できるのが生命保険契約照会制度です。
この記事では、実際に私の親族がこの制度を利用した体験談を交えながら、制度の使い方やメリット・注意点を整理しました。FP(ファイナンシャルプランナー)としての視点も加えてお伝えします。

✏️制度を使うことになったきっかけ(親族の体験談)
私の親族が亡くなったとき、問題になったのが「保険の契約があるのかどうか不明」ということでした。
通帳や書類を探しても見つからず、家族も「どこかの保険に入っていた気がするけど…」という曖昧な記憶しか残っていません。
このままでは保険金請求ができず、相続手続きも進んでいきません。そこで利用したのが生命保険契約照会制度でした。
🗒️実際の申請から回答までの流れ
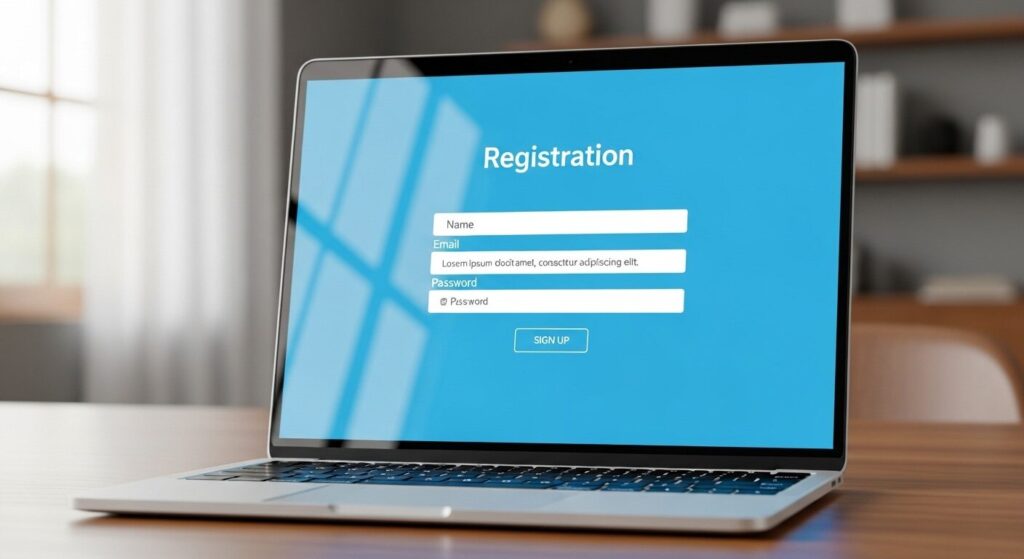
親族が行った流れは以下のとおりです。
- オンラインで申請
- 法定相続人として戸籍謄本(法定相続情報一覧図でも可)や死亡診断書を準備
- 申請する人の本人確認書類をスキャンしてアップロード
- 利用料3,000円を支払い
- 回答が届くまで
- 支払い確認後、約2週間で通知が届きます(書面、オンラインの場合はWebで確認できます)
- 実際には「思ったより早い」という感想でした
- 通知の内容
- 契約の有無と保険会社名のみ
- 保険金額や受取人は加入している保険会社に直接問い合わせが必要
⬇️オンライン申請が下記HPにて可能です

⤴️使ってみて感じたメリット
親族の感想を聞いて、特に強く感じたのはこの3つです。
- 一括照会の便利さ
→ 生命保険協会の会員会社42社にまとめて確認でき、見落としの心配が少ない - 安心感
→ 「どこにも契約がなかったらどうしよう」という不安がほぼ解消される - 費用対効果
→ 3,000円で手間とリスクを大幅に減らせたのは「安い」と感じた
相続の初動でこの安心感は価値があると思います。
⤵️ 課題や不満に感じた点
一方で、次のような課題もありました。
- 書類準備の手間
→ 戸籍や証明書の取り寄せに時間がかかる - 詳細は別途確認が必要
→ 結果通知では「会社名」しかわからず、金額や受取人を確認するには個別に保険会社へ連絡が必要 - 共済は対象外
→ JA共済や県民共済などは、この制度では確認できません - 契約者か被保険者になっている保険しか照会できない →亡くなった人や認知症を発症した人が契約書か被保険者になっている保険のみ確認できます。照会していた人が保険料払っていたでは確認できません。
「万能ではない」というのが率直な感想です。
☀️FPとしてのアドバイス

親族の体験とFPの視点を合わせると、この制度を使うときのポイントは次の3つです。
- 照会代表者を1人に決めること
→ 複数人がバラバラに申請すると手数料が重複してしまいます - 書類はガイド通りに準備すること
→ 書類不備が一番の遅延要因 - 結果が出たらすぐ各社に確認すること
→ 相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)を考える上で金額確認は必須です
✅ 保険会社に連絡するときのトーク例
生命保険契約照会制度で「契約あり」と出たら、次は対象の保険会社に直接連絡が必要です。電話口で困らないよう、以下をご参考にしてください。
電話スクリプト例(死亡保険金請求の場合)
「お世話になります。先日、生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用したところ、御社に契約があるとの通知を受けました。
契約者は【亡くなった方の氏名・生年月日】です。
私は法定相続人(または受取人候補)として、契約内容や保険金請求手続きについて確認させていただきたく電話いたしました。
必要な書類や手続きの流れをご案内いただけますでしょうか。」
電話スクリプト例(認知症等で本人が請求できない場合)
「お世話になります。生命保険協会の契約照会制度で御社に契約があることが確認できました。
契約者である【氏名・生年月日】は現在、認知症で判断能力が低下しており、私が法定代理人として手続きを進める立場にあります。
今後の確認方法や、必要な書類についてご案内いただけますでしょうか。」
👉 ポイント
- 「生命保険協会の照会制度を利用した」と必ず伝える
- 氏名・生年月日を先に伝えるとスムーズ
- 保険会社によって必要書類(戸籍謄本、印鑑証明、委任状など)が異なるので、その場でメモする
📕まとめ
生命保険契約照会制度は、相続や保険金請求の初動でサポートしてくれる制度です。
- 一括で照会できて安心感がある
- 約2週間で結果が届く
- 請求漏れやトラブルを防げる
ただし、共済等が対象外であることや、詳細は別途確認が必要という課題もあります。
親族の体験からも「使ってよかった」という声があり、FPとしても相続の最初の一歩としておすすめできる制度です。
✨関連リンク(内部リンク)


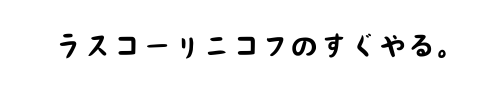
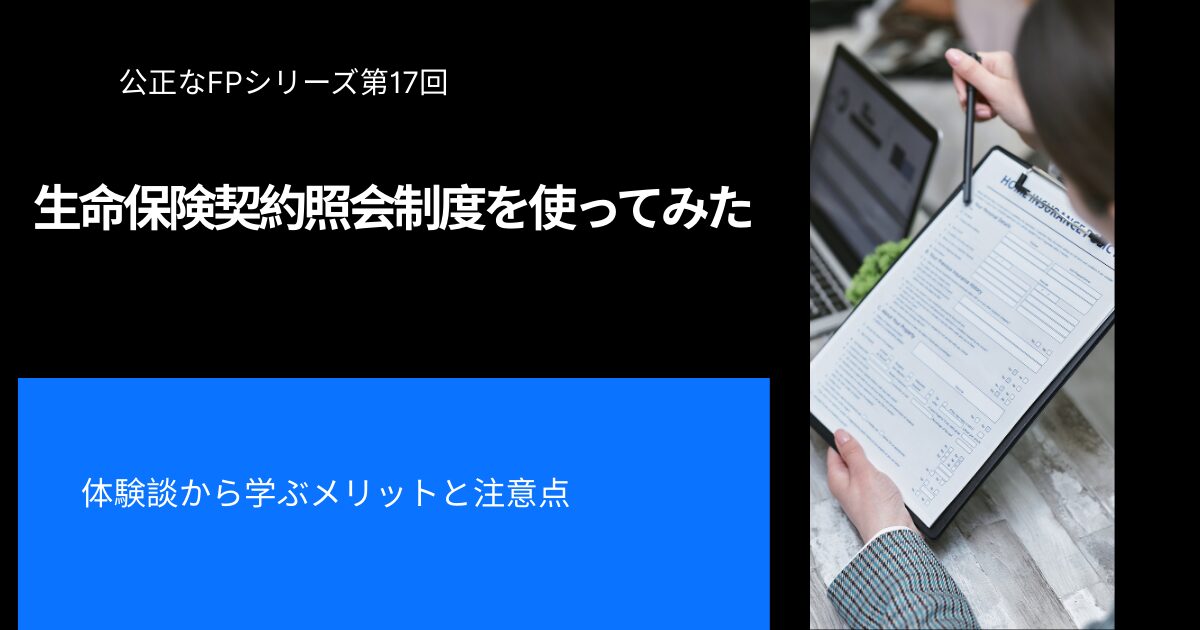


コメント