その1では、開業したての個人事業主(わたし)が「新NISA・iDeCo・小規模企業共済のどれを優先すべきか」を検討しました。
今回は、その続きで「小規模企業共済の出口戦略」です。つまり“もらうときに税金がどうなるのか”です。
この仕組みを知らないと、節税して積み立てた共済金が退職時に思わぬ税負担を受けることもあります。
この記事では、FPラスコルが自分のケースを交えて退職所得控除・1/2課税・年金扱いの違いをわかりやすく解説します。

💬 この記事を読めば
- 小規模企業共済の受け取り時の課税が一目でわかる
- 「退職所得扱い」で税金を最小限にする方法が理解できる
- 途中解約のリスクを回避できる
- 20年以上の長期視点で“安心の老後”が描ける
👉小規模企業共済の受け取りには「3つの出口」がある
| 区分 | 税区分 | 特徴 |
|---|---|---|
| ① 共済金A(廃業・退職時) | 退職所得扱い | 最も有利。控除+1/2課税で税負担が軽い。 |
| ② 共済金B(65歳以上180ヶ月以上払込・事業継続) | 退職所得扱い | 廃業しなくても受け取り可能。節税効果はAと同様。 |
| ③ 老齢給付金(分割受取) | 公的年金等控除 | 年金として分割受け取り。控除があるが総受取額が多いと課税対象に。 |
💬 ポイント
退職所得扱いで一括受け取るのが最も税制優遇が大きい。
分割受け取り(年金扱い)は“老後の定期収入”にはなるが、控除は年単位で分散するため、税的には中立。
📕退職所得控除のルールをFP的に解説
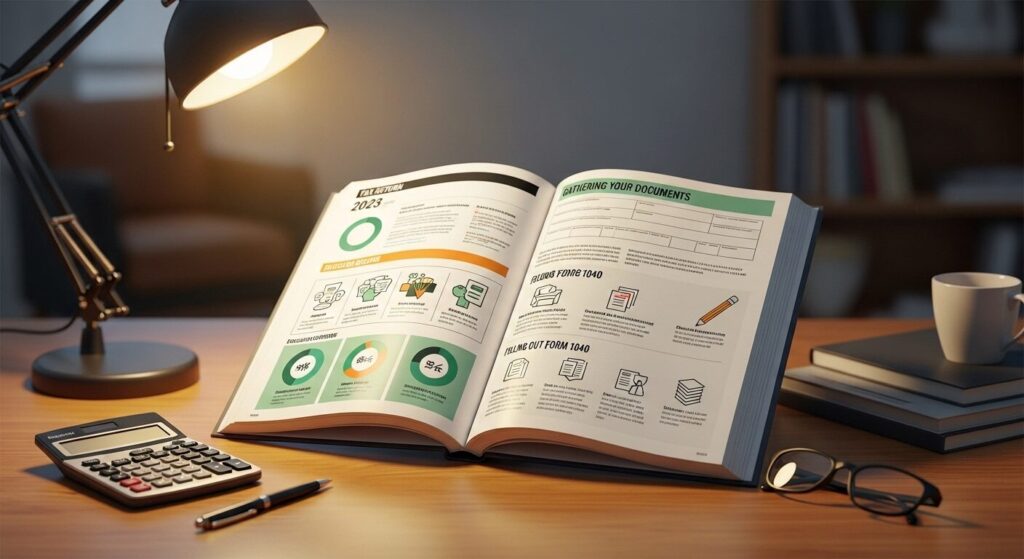
退職所得控除の式はこうです👇
退職所得控除額 =
① 勤続年数20年以下 → 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は、80万円)
② 20年超 → 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20)
そして、課税退職所得の計算式はこう。
(受取金額 − 退職所得控除額)× 1/2
ラスコルの実例シミュレーション(25年積立)
ラスコル
→ 25年間、月3万円ずつ積立(年36万円 × 25年 = 掛金総額900万円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 退職所得控除 | 800万円 + 70万円×5年 = 1,150万円 |
| 受取金額 | 約940万円(積立+利息分 約1.5%複利) |
| 課税対象 | 940万円 − 1,150万円 = 非課税(控除内) |
✅ 結果:税金ゼロ!
→ 控除額のほうが大きいために全額が手取りとなる。
→ しかも積立中の利息は非課税。
つまり、25年以上コツコツ続けると税負担ゼロで退職金がもらえる。
⬇️受け取れる共済金と節税効果を試算できます。
📈年金扱い(分割受取)の場合
「老齢給付金」として年金で受け取る場合は、公的年金等控除が使えます。
| 年齢 | (目安)公的年金等控除額 |
|---|---|
| 65歳以上 | 年金収入110万円までは非課税(目安 他控除との調整あり) |
| 65歳未満 | 年金収入60万円までは非課税(目安 他控除との調整あり) |
👉 たとえば年間100万円を5年分割で受け取るなら、ほとんどが非課税または軽課税で済む目安です。(正確には、専門家やシミュレーションを推奨)
⚠️任意解約(途中解約)は「節税が台無し」に注意
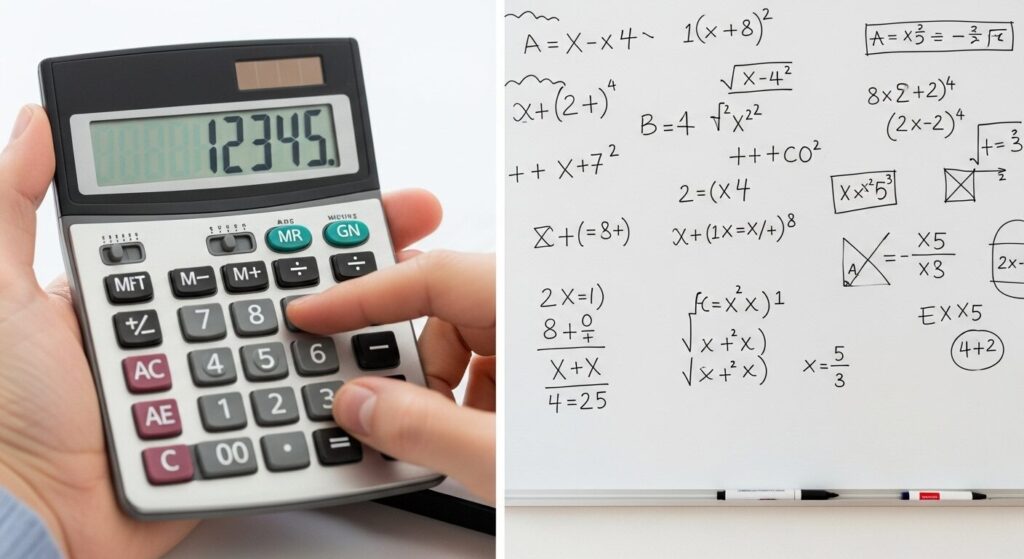
| 解約の種類 | 扱い | 税務上の区分 |
|---|---|---|
| 廃業・老齢による共済金A/B | 有利(退職所得) | 控除+1/2課税 |
| 任意解約(20年未満など) | 不利 | 一時所得・元本割れリスク |
💣 任意解約20年未満でやめると、元本割れ+税優遇消滅。
税務上は、「一時所得」として課税されて50万円(最大)の特別控除後に課税されるので、税負担が比較的重くなる可能性が高い。
このため「小規模共済は、短期節税には不向き」です。
資金が足りなくなったときは、解約ではなく“貸付制度”を使うのが鉄則。
🚪出口戦略まとめ(表)
| 受取タイミング | 税区分 | 主な控除 | 税率軽減度 | FPラスコル推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 廃業・退職時一括 | 退職所得 | 退職所得控除+1/2課税 | ★★★★★ | ◎(最強) |
| 65歳以上継続受取 | 退職所得 | 同上 | ★★★★★ | ◎ |
| 分割(年金)受取 | 公的年金等控除 | 年金控除110万 | ★★★ | ○ |
| 任意解約(短期) | 一時所得 | 50万円控除のみ | ★ | ×(避ける) |
☀️出口設計のゴールデンルール【FPラスコル流】
1️⃣ 20年以上継続を前提に加入(節税+退職控除フル活用)
2️⃣ 廃業時に退職所得扱いで一括受取
3️⃣ 資金が必要なときは解約せず貸付制度を利用
4️⃣ 黒字安定後に掛金を増額(7万円上限)
5️⃣ 他の退職金と同時受取しない(控除が按分され減るため)
✨ラスコルの実感(まとめ)
私は、開業したて。収益がまだ安定していないので共済は、月1,000円から開始します。
黒字化後は毎年掛金を見直して、将来的には退職所得扱いで一括受取を選択。
25年間コツコツ積み立てて控除範囲内で非課税で受け取る予定──
それが私の「未来の自分への退職金戦略」です。
小規模企業共済は“節税+退職金+安心”の三拍子。
ただし、途中で投げ出すと損をする制度です。
長く続けた人ほど得をする――それが本当の“小規模企業共済の威力”です。
✏️その1からの学びと最終まとめ

| フェーズ | 優先制度 | 狙い |
|---|---|---|
| 開業初期 | 新NISA | 非課税運用・柔軟性 |
| 黒字安定期 | 小規模企業共済 | 節税+退職金積立 |
| 高所得期 | iDeCo | 老後資金・長期控除 |
👉 そして、小規模企業共済の出口は「退職所得控除+1/2課税」=“ほぼ非課税の退職金”
を手にすることが可能。
開業した今こそ、20年後・30年後を見据えて仕組みを理解しておこう。
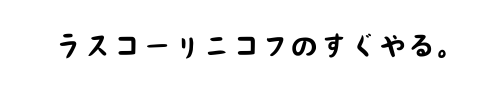
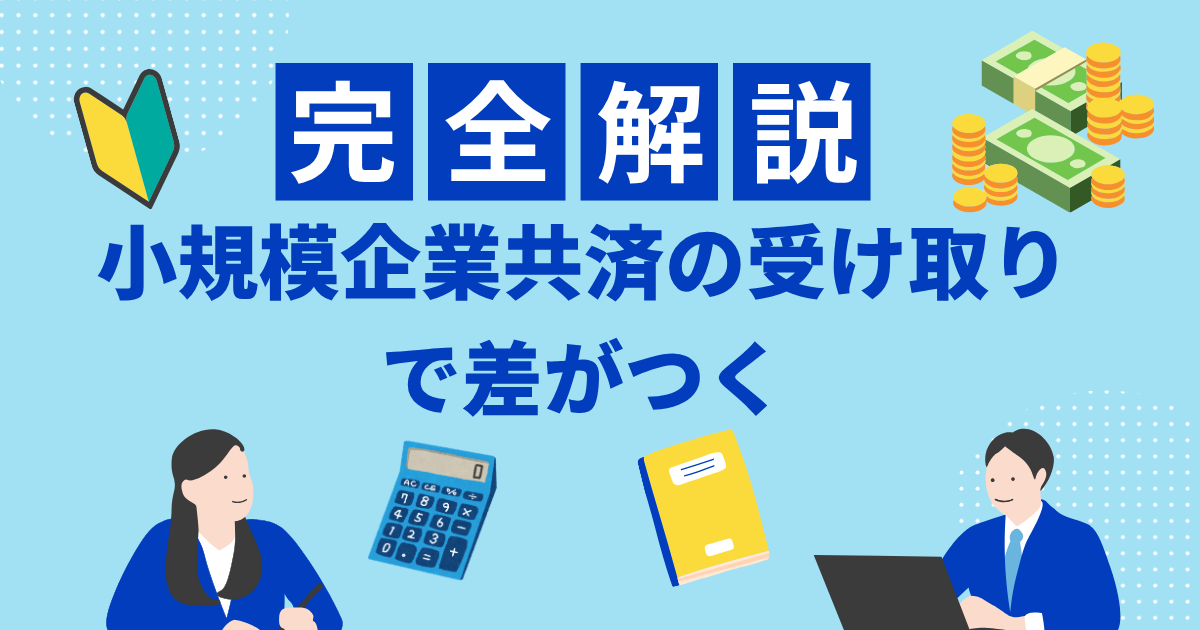


コメント